およそ80ページでも大いに学びを得られる1冊。親子関係に悩むあなたに深く刺さる内容です。
今回の本のご紹介
今回は、著者:野口 嘉則さんの『完全版 鏡の法則』をご紹介いたします。
※注意事項
本記事では、「親子関係と子どもの自立」をメインに取り上げております。
タイトルとなっている「鏡の法則」についても多少触れております。
しかし、その効果や本質については深く触れておりません。
予めご了承ください。
この本の学びポイント
本書のテーマを話す前に、まずは著者をご紹介。
著者は野口嘉則さん。本書では「家族関係」と「自己実現」の専門家と紹介されています。
また、完全版発売にあたり、出版社「サンマーク出版」より以下のように紹介されています。
解説は、前作で反響があった親子関係の問題について大幅に加筆修正しています。
https://bookstore.sunmark.co.jp/products/9784763135025
そこで今回の記事でとりあげるテーマは、「親子関係と子どもの自立」
実は次のような悩みは「親から受けた教育」の影響かもしれないのです。
📍他人からの頼みごとを断れない
📍いい人を演じようと人間関係に疲弊する
📍他人の言動にゆるせないことがある
これから子育てをする方にも間違いなくお役に立てる内容。
ぜひとも、この本を通じであなたの親子関係について見直していただきたいです。
こちら『完全版 鏡の法則』は、物語形式となっております。
そこで、まずは「鏡の法則とは?」という点を踏まえ本書のあらすじから見ていきましょう。
この本の概要
あらすじ
主人公の栄子は、小5の息子がいじめられていることに悩んでいました。
息子のことについてはそこまで口を出そうとしない夫に不満を持つ栄子。
この事態を何とかしたいと思いながらも、有効な方法が見出せずにいる日々。
あるとき、夫伝いでコンサルタントの矢口に出会い、悩みを打ち明けました。
矢口は「鏡の法則」を説きながら、問題解決を図りました。
すると、今栄子が抱えている問題は、栄子と栄子の父親との関係にあったのです。
長年わだかまりを抱えていた父親との関係を見直しすことで、栄子の心が変わっていくのです。
鏡の法則とは
鏡の法則とは「私たちの現実は私たちの心を映し出す鏡である」という原則。
人生においては、自分の心の波長に合った出来事が起きてくるということなのです。
本書に当てはめると、次の通り。
現実:小5の息子がいじめられている
⇓ 鏡の法則を用いて、
栄子自身、誰かを責めている問題がある。
それが、栄子の父親との関係であったことに気づく。
まとめると、この鏡の法則を以下のように活用するのです。
自分の人生に起きていることを見ることによって、自分の心のありようを推察する。
そうして、自らを変えるヒントを探るのです。
親子問題に関する要点3選
ここからが本記事の本題となります。
鏡の法則を用いて、親子問題の解決に努めることとなった栄子。
本書では、この親子問題に関して深く解説されています。
他人をゆるす
この物語で父親との問題を解決するために、父をゆるすことに努めました。
父をゆるすために行ったのが、以下の2つ。
1️⃣自分自身をしっかりと守る
相手と自分との間に適切な境界線を引く。
そして、相手から振り回されない状況を作る。
なお、本書ではすでに父親と離れて暮らしていたため、栄子はこの点はクリアしていました。
2️⃣感情を吐き出す
相手の怒りや恨みの感情を紙に書きなぐる。
そうすることで、その背景にあったつらさや悲しみにアクセスできます。
怒り・恨みから、つらさ・悲しみの感情をも吐き出せるようになるのです。
本編では、栄子は実際に紙に記しました。
そうするこで徐々に父親への気持ちに寄り添うようになりました。
そして、父親にその感情を伝えることで、父親をゆるすことができたのです。
【Point】
ゆるすことで過去の出来事から解放され、相手を責めることをやめる。
その結果、心の中で安らぎを選択できるようになる。
過干渉・過保護な親
では、過干渉・過保護な親の場合どうでしょうか。
1️⃣自分自身をしっかりと守るで挙げた、相手と自分との間に適切な境界線を引くこと。
この点がものすごくハードルが高くなります。
例えば過干渉・過保護な親はこんな行動を取りがちです。
・勝手に入ったり、日記を読んだりする。
・何も相談していないのに、子ども同士のけんかの解決を図ろうとする。
・「自由に決めてもいいよ」と言ったのに、子どもが選んだものに対し不機嫌になる。
このように親が子どもをコントロールしようとすると、子どもは親と境界線を引けなくなります。
そして、子どもは親の機嫌や態度に気を遣うになります。
自分の気持ちを抑えてでも親の期待に応えるようとするのです。
このような子どもは反抗期を迎えることなく大人になっていきます。
他人との境界線を引くことが上手く習得できないまま大人になると、
📍他人からの頼みごとを断れない
📍いい人を演じようと人間関係に疲弊する
📍他人の言動にゆるせないことがある
自立できないまま、こういった人間関係の問題を抱えてしまうのです。
【Point】
過干渉・過保護な親の教育を受けた子どもは「ノー」と言うのをためらってしまう。
そうして大人になって、社会に出ると対人関係で苦しむこととなる。
反抗期の必要性
反抗期は子どもの自立に必要不可欠な期間だと本書で述べられています。
反抗期の意義は次の通り。
反抗期によって、子どもは親との間に境界線を引くことができる。
そして、親の呪縛から脱することができる。
⇓ つまり、
子どもが自立するため、親が子離れをするための関門となる期間である。
そのため過干渉・過保護の下で育てられ、今、対人関係に悩んでいる方へ。
今から反抗期をやり直すことをオススメします。
ポイントは、親との間にしっかりと境界線を引くこと。
反抗期のやり直しとは具体的に、
1️⃣親と自分との間に適切な境界線を引く。
・物理的に親と離れて暮らす
・「ほっといてほしい」「必要以上に電話してこないで」ときちんと伝える
2️⃣感情を吐き出す
今まで抑えてきた我慢や、怒り、つらさを紙に書いていってみてください。
この2つを行うにあたって、ためらってしまう人もいらっしゃるかと思います。
でも、今から書くことを心に留めてほしいのです。
自分は自分。親は親。
適度な距離を取り、どうか親を責めることを自分に許可していただきたいです。
親との間で傷ついたことの責任を全てあなたが引き受ける必要なんでないんですよ。
【Point】
反抗期のやり直しを完遂することで親から自由になれる。
親から自由になれることで、親を心からゆるすことができる。
実生活への応用
鏡の法則
自分の人生に起きていることを見ることによって、自分の心のありようを推察する。
そうすることで、自分自身の問題解決を図る。
これが鏡の法則ですが、間違えてはいけないことが1点あります。
あくまで鏡の法則は、問題の解決策の1つに過ぎないということです。
例えば、他者の言動によって嫌な思いをしている場合、
適切な解決策は、
・直接相手に言う
・他の人に相談してみる
このような外部への働きかけが有効的です。
そのため、問題解決は次のようなステップを意識してみてください。
Step1:まずは外部に働きかける
Step2:鏡の法則に従い、自分の心の中を見つめ直す
Step3:なかなか原因が見つからなければ、今自分ができることを全うする。
家族問題
自分の親が、過干渉・過保護な親、もしくはいわゆる毒親で、今現在苦しんでいるあなたへ。
上述の要点で記載したことに加え、一つ提案させていただきます。
ずばり、カウンセリングへの相談です。
本物語では、栄子は夫伝いで知り合った矢口さんに悩みを打ち明けました。
この二人って関係性が遠く、いわば他人ですよね。
心に蔓延る問題って関係性が近い人より、関係性が遠い人の方が話しやすいと思うのです。
そこでカウンセリングでご自身の悩みを打ち明けてみてください。
まさに、感情を吐き出すには最適な環境です。
幼少期に受けたことをゆっくりと思い出しながら話すことで、自然と感情を吐き出せます。
そうして、固執していた「自分の気持ちを抑えでも相手の期待に応えるようにする」という考え方がゆっくりと時間をかけつつも変わっていくはずです。
まとめ
人生で起きるどんな問題も、何か大切なことを気づかせてくれるためである。
辛いことを乗り越えたら、「あの時が人生の分岐点だった」と思えるもの。
鏡の法則を活用することで、あなたの自身の問題にきっと気づけるはずです。
また、この著書を通じて、親子関係を見直し、子どもの自立を後押しする。
本書はそんな親子問題の入門書ではないかと私は考えています。
こういった親子関係と子どもの自立に関する著書はたくさんあります。
まずはこの本を読んでいただき、他の専門書を読んでみるのはいかがでしょうか。
最後に今、子育てをされている方へ。
あなたは最近、子どもについ言いすぎてしまったことはありませんか?
次にその場面が来たら、「信じて見守る」ことを意識してみてください。
あなたにとって大切なお子様。
本当の意味で、お子様の味方になってあげてください。
さらに!!
👇あわせて読みたい
嫌な問題ってなんだか立て続けに起きてしまう気がする。。。
それって実は否定的に考えすぎなのかも。
もっと心穏やかに生きるための考え方を知りたい方はこちらの記事をチェック!
うまくいっている人の考え方
この本を読んでみたい!と思われましたら、ぜひリンクからチェックしてみてください⏬
<ゆーの勉強部屋-Instagram>
https://www.instagram.com/yuu_studyroom/
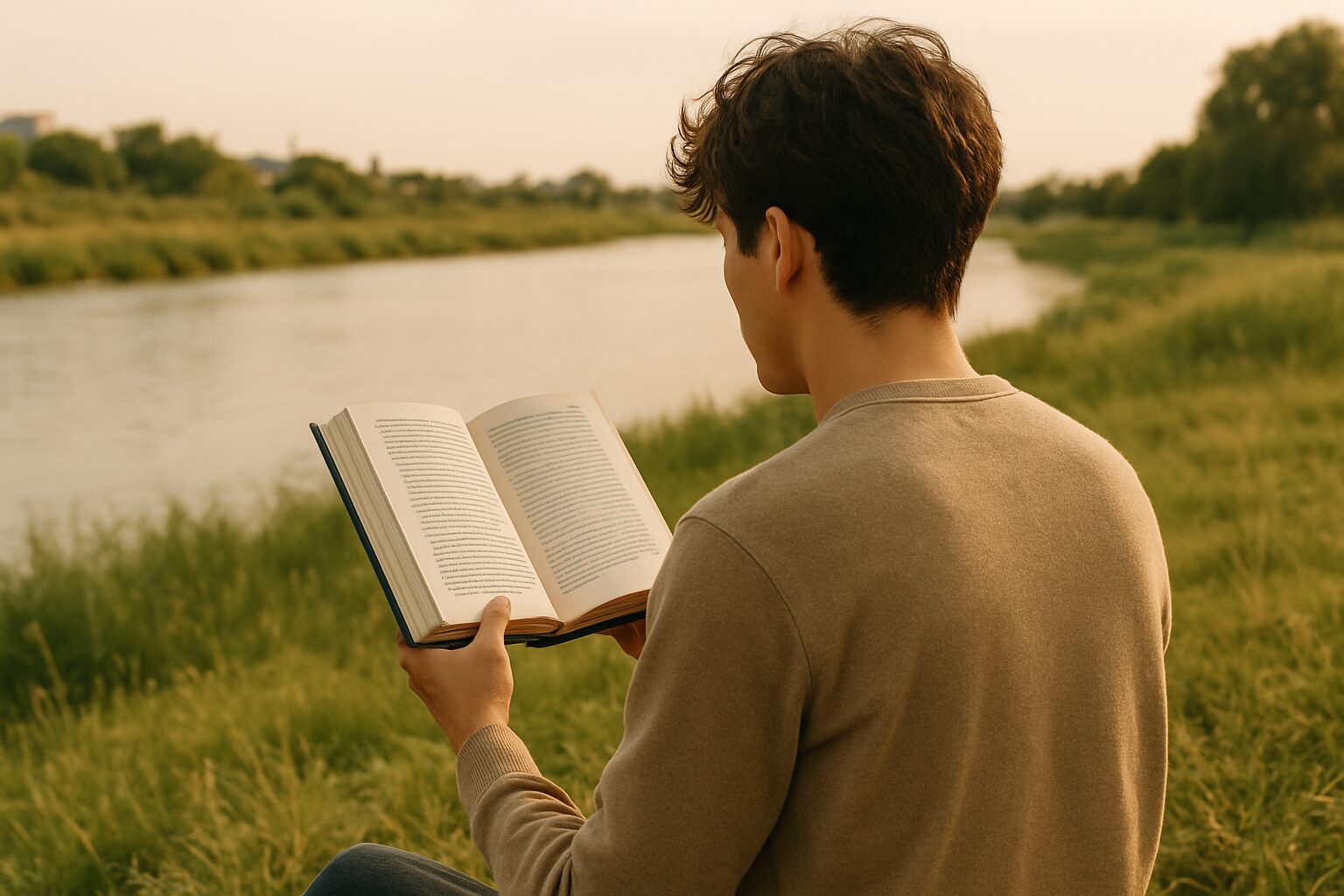


コメント