ただ寝ても休めていない?!あなたはほんとに疲れが取れていますか?
今回の本のご紹介
今回は、著者:片野 秀樹さんの『休養学: あなたを疲れから救う』をご紹介いたします。
この記事をご覧のみなさま、毎日のお仕事・家事・育児など本当にお疲れさまです。
みなさまのお疲れ具合はいかがなものでしょうか。
📍いつも体が重い
📍休日はゴロゴロしている…
📍毎日の仕事や家事が忙しい…
正直、疲れてない人っているの?と疑いたくなります。
こちらの本によると、なんと日本人の8割もの人が疲れているんです。
そんな毎日お疲れさまのあなたに質問。
「あなたは正しく休めていますか?」
実は日本人の多くが間違った休み方をしているのです。
この本の学びポイント
この本の学びポイントは、「正しい休み方」
著者の片野秀樹さんは「休養学」の第一人者。
疲労が蔓延している現代の日本に「休養」の意識改革を掲げられています。
とりあえず寝たら休めるんじゃないの?と思ったそこのあなた!
もちろん体をふんだんに使っていれば寝て疲労を回復できます。
しかし現代はデスクワークが多く主に疲労しているのは脳なのです。
これでは寝てもあまり休むことができてないんです。
となると、現代社会における正しい休養法を知っておくべきですよね!
そこで本記事では、
1️⃣「休養学」とは?
2️⃣最高の「休養」を取る7つの戦略
3️⃣「休み方」に関する新しい観点
以上の3点を要約してまいります。
この本の要点3選
「休養学」とは?
健康づくりの三大要素は、「栄養・運動・休養」と言われています。
しかし、考えてみると休養だけ学べる場所がどこにもないんです。
そこで、著者の片野さんが提唱されたのが「休養学」。ただ寝たりボーッとしたりするのではなく、主体的な疲労の回復の仕方・休み方を提示されています。
疲労を甘く見てはいけません。
疲労は病気につながる重要なサインなのです。
では休養学で述べられている疲労の回復はどのようなものでしょうか。
一般的なサイクルは以下の通り。
「活動」→「疲労」→「休養」
一方、本書で提示されているサイクルは以下の通り。
「活動」→「疲労」→「活力」→「休養」
この活力がポイントなのです。この活力については次節でご説明いたします。
【Point】
脳が疲れている現代。寝るだけでは疲れは取れない。
ポイントとなるのは、活力にある。
最高の「休養」を取る7つの戦略
活力とはズバリあえて負荷をかけることです。
あえて自分に何か負荷をかけることで活力を高める。
そしてもう一度しっかりと休養の時間を取るのです。
具体的に「負荷をかける」とは、以下のようなもの。
<肉体的な負荷>
・軽い運動やウォーキング
・ゆくゆくはランニングに移行する
<精神的な負荷>
・難しい資格に合格する
・趣味の世界で何かの賞に応募する
・山登りで百名山制覇する など
こういった休養の取り方を、この本では”攻めの休養”と呼んでいます。
この攻めの休養について、休養学では7タイプ定義しています。
7つのタイプの中の一つに運動タイプがあります。
休養学では運動を休養の一種とみなしています。
適度な運動をすることで、より疲労回復が進むからです。
昼間に適度な運動をすると体も疲れるため、夜に深い睡眠がとれる効果もあります。
<おすすめ>
・ヨガ
・ストレッチ
・ウォーキング など
休養の7タイプは他にも「親交タイプ」や「娯楽タイプ」などございます。
気になる方はぜひこの本を読んでみてください。
【Point】
あえて負荷をかけることで、疲労の回復が雲泥の差となる。
攻めの休養の本書のキーワードである。
「休み方」に関する新しい観点
あなたの思い浮かぶ1週間。たいていは日曜日をスタートとしています。
この発想、ちょっと変えてみませんか?
週末が始まる土曜日を基準に、次の月曜日からの1週間の日程を俯瞰するようにしてみる。
本書ではこの考え方が勧められています。
土日月火水木金
土日でたっぷりと休養にあてて、100%に充電しておく。
そして、月曜日から少しずつ消耗してて金曜日でほぼ使い切る。
本書ではこれが理想の形だと述べられています。
「平日のあとの土日で休む」
↓
「土日に休んだ分で平日働く」
という意識に切り替えるんです。
【Point】
休日への意識を変えるだけで休養の効果は格段に変わる。
休日への意識改革を試してみませんか。
実生活への応用
本書でも取り上げられていますが、まずは休みの取り方について考えてみます。
・仕事が落ち着いたら休もう
・ヒマになったら休みをとろう
このように、仕事を基準に休みを取っていないでしょうか。
そうすると、疲れ切った状態で休暇に突入することとなります。
そこで、
「疲労してから休むのではなく、疲労しそうだから先に休んでおく」
という考えを取り入れてほしいのです。
予定される活動から逆算して、必要な力を蓄えておくという発想に切り替えるのです。
そして次に”攻めの休養”を取り入れる。
・上述のように運動を取り入れて、リフレッシュする。
・日曜大工やDIYといった趣味を楽しむ。
・習い事や読書などで新しい知識を取りいれる。
など、ただぼーっとするのではなく、活力を得られるように休む。
そうすることで、疲労回復を促進するのです。
土日に攻めの休養を取り入れ、疲労回復したエネルギーを平日に使っていく。
そして金曜日に使いきったら週の始まりである土曜日から休養する。
このサイクルを繰り返していくのです。
最後に
最後まで読んでいただき誠にありがとうございます。
今回初めての投稿ということもあり、みなさまにとって読みやすく書けているかが、大変気になります。
今回の記事で少しでもこの本に興味を持ってもらえればとても嬉しいです。
今回書いた内容以外にも睡眠や疲れについて、また攻めの休養について詳しく書かれていますので、ぜひ一度読んでみてください。
今後もこのような形式で私自身が紹介したいなと思った本をまとめていきたいと思っています。
どうぞ、当ブログ「ゆーの勉強部屋」をよろしくお願いいたします。
この本を読んでみたい!と思われましたら、ぜひリンクからチェックしてみてください⏬
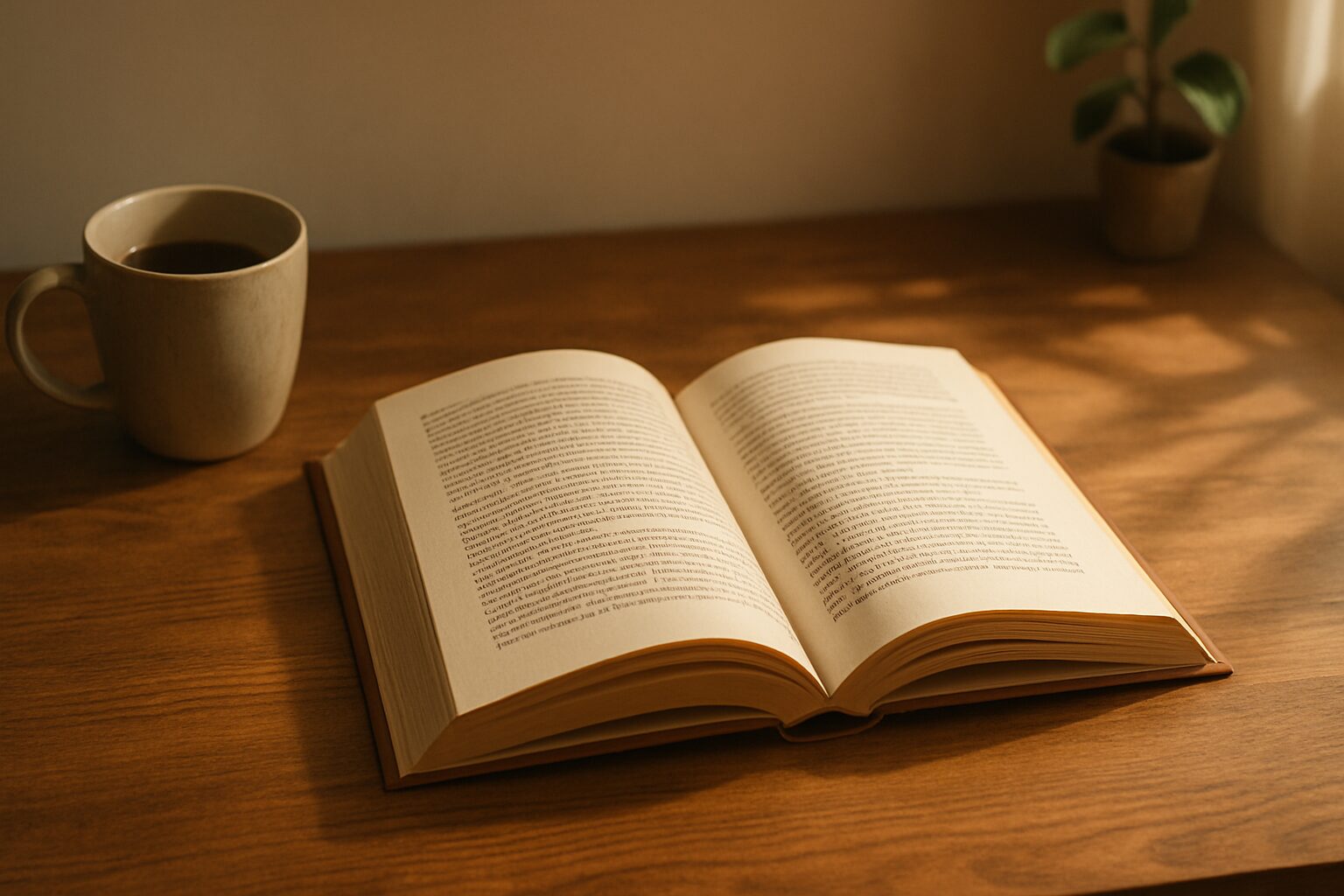

コメント