ただ「やばい」じゃ終わらせない。この本で、あなたの表現力は格段に上がります。
今回の本のご紹介
今回は、著者:三宅 香帆さんの『「好き」を言語化する技術』をご紹介いたします。
自分のブログが読者に響き、ブログを通じて自分のことを好きになってほしい。
こんな願望を私は抱いています。
だからこそ、自分の言葉で文書を書く大切さを実感しています。
例えばみなさんはSNSで本の感想を書くとき、こういった表現になりがちではないでしょうか?
・あの小説のどんでん返しはやばかった!!
・あの本、マジでおもしろかった!!
本書は、好きな作品・趣味・推しを言葉にしたいけれど、上述のようなあきりたりな表現しか出てこない人向けに書かれた一冊となります。
この本の学びポイント
本書のテーマは「自分の言葉をつくる技術」。
著者の三宅香帆さんは文芸評論家。
三宅さんが文芸評論家として発信している文章は、本という名の「推し」の魅力について解説しているものがほとんどです。
そんな三宅さんが執筆する本書では、SNS、ブログ、ファンレター、雑談など。
さまざまな場面において、推しの魅力を”自分の言葉”で伝える技術がたくさん紹介されています。
📍ブログやSNSで、好きなことについて書きたいけれど、どう書けばいいかわからない
📍自分の大好きなものについて語るネタをどうやって見つけたらいいかわからない
📍自分には誰かの心に響くような語彙力や表現力がない
そう思っているそこのあなた!
ほんと、もったいない!!
自分の感想を言葉にするちょっしたコツを知っていればそんな悩みからはおさらばできちゃいます。
本記事では推しの素晴らしさをSNSやブログで発信するための3ステップをご紹介いたします。
この本の要点3選
Step1.前準備・心がけ
先に自分の「好き」を言語化する上で、最も大切なことを書きます。
ずばり、「他人の感想を見ないこと」です。
こんな経験ないでしょうか?
自分にとってすごくおもしろかった映画。でもSNSを見ると不評が目立つ。
・あれ?自分の感想って変かな?
・何だか他の人のレビューの方が説得力がある…。
特に自分と反対の意見が強い言葉で述べられていたとき、その意見に引っ張られてしまった経験ありませんか?
人は他人の言葉に影響を受けてしまう生き物。
他人の強い言葉に影響を受けると、自分の感情や思考、さらにはもともと抱いていた言葉を見失ってしまいます。
逆に先に自分の感想を書いてから他の人の感想を見ると、「なるほど、そういう風に思うんだ」と客観的に見られるんです。
【Point】
まずはまっさきに自分の感想をメモする。
SNSやインターネットで他の人の感想を見るのは、自分の感想を書き終わってから!
Step2.自分の言葉をつくる
自分の言葉をつくるためにメモを取る。
ここではそんなメモを取るまでの3段階のプロセスを紹介いたします。
1️⃣よかった箇所の具体例を挙げる
何かを読んだり観たりしたときに、「どの部分がよかったか?」を具体的に取り出すステップです。
「どのシーン?」「どのセリフ?」「どの描写?」とできる限り具体的な箇所に焦点を当ててください。
2️⃣感情を言語化する
具体例をもとに「自分はなぜそれを“よい”と感じたのか?」を探り、自分の中に起きた感情を言葉にするステップです。
ただ「嬉しい」「悲しい」とするのではなく、もっと細分化して表現するのです。
どういった理由で嬉しく感じたのか、何が原因で悲しく感じたのか。
自分の言葉で感情を言葉にしてみましょう。
3️⃣忘れないようにメモする
せっかく見つけた「好き」や感情は、時間とともに薄れていってしまうため、メモとして残すステップです。
形式は自由です。スマホに残したり、非公開のブログに書いたり。
自分だけのメモをつくることが、あなたのオリジナルな感想を生みだします。
【Point】
この3ステップを踏むことでありきたりな言葉や他人に借りた言葉ではなく、“自分の言葉”が育っていく。
Step3.SNSやブログで発信する
Step.2でまとめたメモをベースに自分の言葉を使ってSNSやブログで発信していきましょう。
書く内容に困ったら、メモや推すもの自体を見直してください。
短文となるSNSの場合、コツとなるのはこちら。
ずばり、「自衛」です。上旬の通り、SNSは他人の影響をうけやすい。
だからこそ、「他人の言葉に自分が影響されないように、自分の言葉を守ること。」
これがSNSのコツとなります。
長文となるブログの場合、コツとなるのは以下の2点。
①読者を決める
②伝えたいポイントを決める
ブログで大事なことはそのブログのゴールをしっかりと意識して書くことす。
そのために、想定した読者に伝えたいことが伝わっているかが大事になります。
私もブログを書くときはこのことを意識しています。
果たして読者であるみなさんに伝えたいポイントが伝わっているか。
常に気になっているところです。
【Point】
SNSとブログで意識すべきべきポイントは異なる。
書く内容に迷ったらもう一度推すものを見直す。すると新しい切り口が見えてくる。
実生活への応用
いやいやSNSやブログで発信なんてしないよという方もいらっしゃると思います。
実はこの本は、ビジネスシーンでも役に立つと私は考えています。
①プレゼン・企画書で「共感を呼ぶ言葉」を使えるようになる
<活用方法>
「自分がなぜこの企画を推奨するのか」「なぜこの提案が大切だと思うのか」を、表面的なデータだけでなく実感を伴う言葉で語れる。
<メリット>
・聴き手の感情に訴え、説得力が増す。
・「想い」や「ストーリー」を伝えることによって共感が生まれる。
②自己理解とキャリア設計に役立つ
<活用方法>
「自分が本当にやりたいこと」や「何にモチベーションを感じるか」を、内省を通じて言語化し、キャリア選択や職務への向き合い方に明確な軸を持つ。
<メリット>
・転職・面接・1on1で、自分の価値観を言語化できる。
・モチベーションが保ちやすくなる。
③クリエイティブ・マーケティングで差別化される言葉がつくれる
<活用方法>
商品・サービスの「好き」「魅力」「推しポイント」を表層の特徴ではなく、深い実感や感情から語る。
<メリット>
・コピーや広告文にリアリティと温度感が出る。
・商品の“ファン視点”を言語化できる。
このように、自分の感情を言語化するという点で、この本はビジネスシーンでも有効な一冊なのです。
まとめ
『「好き」を言語化する技術』は、
自分の好きなもの、推しの魅力を、自分の言葉で伝えたいすべての人に向けた一冊となります。
まずは「なぜ好きなのか」を丁寧に掘り下げて、あなたの“好き”をあなたの言語で表現してみてください。
あなたが最近、「おもしろかった」「誰かにこの感動を伝えたい!」と思った瞬間はありましたか?
そのとき、自分はどう感じ、なぜ心が動いたのかを言葉にして、ぜひ共有してほしいです。
さらに!!
👇あわせて読みたい「書く習慣を定着させる方法」についてはこちらから!
書く習慣 ~自分と人生が変わるいちばん大切な文章力~
この本やばい!読んでみたい!と思われましたら、ぜひリンクからチェックしてみてください⏬
<ゆーの勉強部屋-Instagram>
https://www.instagram.com/yuu_studyroom/
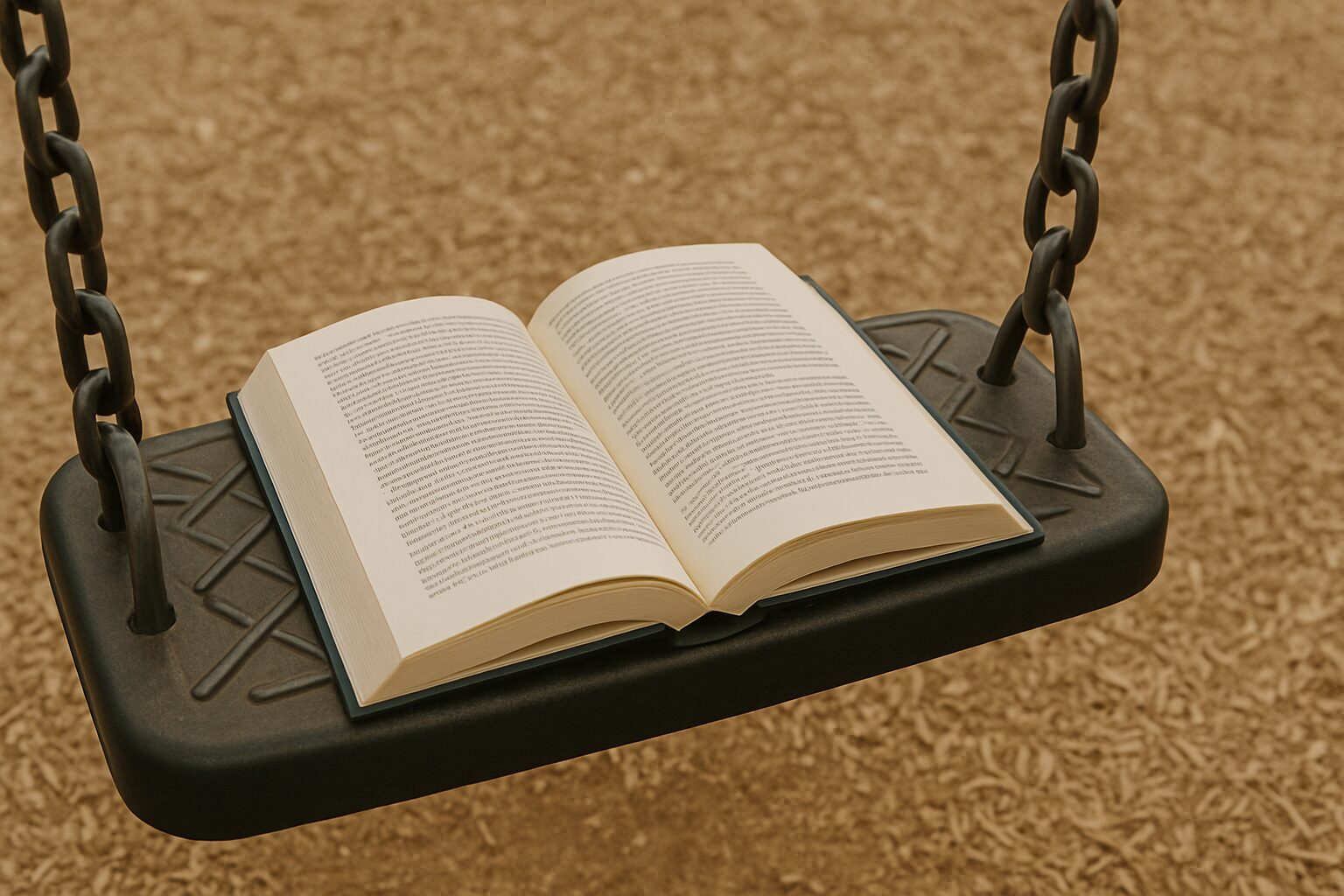

コメント